Fooled by Randomnessを学んだ結果(要約)
こんにちは。今回は、ナシーム・ニコラス・タレブさんの『Fooled by Randomness(邦題:まぐれ)』を読んで、「あ、これ人生の見え方が変わるかも…」と思ったので、フランクな敬語でわかりやすく要約していきます。
この本のテーマはズバリ、「人はどれだけ“運”に騙されているか」。
特に投資の世界やビジネス、スポーツの成功なんかでありがちな“勘違い”をぶった斬っていく内容です。
1:成功してる人が「実力者」とは限らない
まず、タレブさんははっきり言います。
「成功=実力」とは限らない。
「たまたま運が良かっただけ」の場合もめちゃくちゃ多い。
例えば、1000人の投資家がいたとして、毎年ランダムに売買していたら、10年後には1人くらい“超勝ち組”が現れます。でもその人は「実力」で勝ったのか、「まぐれ」だったのか、判断がつきにくいんですよね。
成功には“運”が紛れ込んでいる。
この視点が抜けると、人は簡単に「自分は天才かも」と勘違いします。
2:人間は「意味を作りたがる生き物」
人って、偶然の中に“意味”を見出すのが好きなんです。
例えば、ある会社が急成長したとき、「社長の経営手腕がすごい」とか「この商品がウケたから」といった理由づけをしたくなります。でも実際には「時代の流れ」や「競合の失敗」といった偶然の外部要因が大きく関わっていたりします。
タレブさんはそれを「ナラティブの罠(物語化の罠)」と呼んでいます。
3:失敗は目に見えにくい
成功者ばかりが目立つ社会では、「失敗者の山」が見えにくくなります。
例えるなら、戦争から帰還した戦闘機に穴が空いてる場所を補強する、という話。実は「帰ってこられなかった機体」がどこに被弾していたのかを見ないと、本当の弱点はわからない。
同じように、生き残った成功者だけを見て分析しても、真実にはたどり着けないんです。
4:人は「確率」が苦手
タレブさんは、人間の脳は確率をうまく扱えないと語ります。
例えば、
- コインを10回投げて、10回表が出たら「次は裏が出るはず」と思う
- 小さな勝ちが続くと「自分はツイてる」と思ってリスクを取りすぎる
こういった「確率の錯覚」によって、人はしょっちゅう間違った判断をしてしまうんです。
5:「再現性のない成功」に要注意
例えば、短期的に大儲けした投資家やトレーダーがいたとしても、それが本当に“実力”だったのかどうかは、長期的に見ないとわかりません。
「成功者の真似」は、実はかなり危険。
表面的なテクニックよりも、その裏にある「再現性のある考え方」や「リスクとの付き合い方」を学ばないと、いつか運が尽きたときに破滅します。
6:「ランダムさに強い人」が勝つ
この本でタレブさんが強く伝えているのは、**「運や偶然とどう付き合うかが、人生の分かれ道になる」**ということ。
・運に過信しない
・成功しても自惚れない
・失敗しても自分を責めすぎない
・運が悪くてもコツコツ続ける
こういった“ランダムさを前提とした生き方”こそが、実は地に足のついた考え方なんです。
7:結局、地味な思考力が一番強い
タレブさんが提唱するのは、地味だけど本質的な思考法です。
- 「データを見るときは、生存バイアスに気をつけよう」
- 「偶然を偶然として認識しよう」
- 「一発逆転より、小さな成功を重ねよう」
- 「自分の判断が感情に引っ張られてないか冷静に考えよう」
こういう視点って、高校生にもめちゃくちゃ大事なスキルだと思うんですよね。
部活でも受験でも、結果がうまくいった/いかなかっただけで判断するのではなく、「その結果はどんな背景があったのか?」と考えることが、思考の筋トレになります。
【まとめ】「まぐれ」に惑わされずに生きる方法
『Fooled by Randomness』を通じて学べる最大のことは、
「世界は“まぐれ”でできてる。だからこそ、自分の判断を磨くしかない」
というシンプルな事実です。
- 誰かが成功しているのは「たまたま」かもしれない
- 自分が失敗したのも「たまたま」かもしれない
- でも、そこから何を学ぶかは、完全に自分次第
だからこそ、表面的な結果じゃなく、自分の「思考スタイル」や「判断力」に投資しようというのが、この本の大切なメッセージです。
【おまけ】ブラック・スワンとセットで読むと最強
ちなみに、『ブラック・スワン』と『Fooled by Randomness』は、タレブ思考の“前編・後編”みたいな関係です。
・『Fooled by Randomness』は「人間は偶然をどう誤解するか」
・『ブラック・スワン』は「予測不能なことが世界をどう変えるか」
この2冊を読むと、「世の中って自分が思ってたより全然読めないし、だからこそ備えることが超重要なんだな」と納得できると思います。

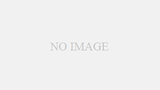
コメント