会社の数字はウソをつく を学んだ結果(要約)
こんにちは。今日は「数字」を信じすぎると痛い目に遭う、という話です。
企業の決算書って、どこか神聖で、まるで“真実の書”みたいに思っていませんか?
でも実は…その中には、巧妙なトリックや仕掛けが潜んでいることもあるんです。
今回ご紹介するのは、ハワード・シュリッドさんとジェレミー・ペルツさんが書いた『会社の数字はウソをつく(Financial Shenanigans)』。
タイトルからしてヤバそうな匂いがしますよね。でも、その直感、正解です。
この本は、「いかにして企業が決算書をごまかすか」をテーマにした、いわば“数字の嘘”の暴露本。
でも怖がる必要はありません。今日はその内容を、できるだけカンタンに、そしてリアルにお伝えします。
なぜ企業は数字をごまかすのか?
まず大前提として、上場企業って「株価」がめちゃくちゃ大事なんです。
なぜなら、株価が下がれば経営者の評価も下がるし、場合によってはクビになります。株主からのプレッシャーも凄い。
だから彼らは「良く見せたい」と思う。そうなると、出てくるのが“数字のマジック”なんです。
言い換えれば、「現実はイマイチだけど、見た目だけはイケてる風にしたい」ってこと。
で、それをやる場所が、財務諸表(決算書)ってわけです。
数字のトリックって、たとえば何?
本書では「シェナニガン(Shenanigans)」という言葉を使っています。
これ、英語で「ずる賢いごまかし」とか「インチキ」って意味。
では、実際にどんな“数字のごまかし”があるのか、例をいくつか紹介します。
1:売上の“前倒し”計上
ある会社が「来月の売上になりそうな案件」を、今月の売上にしてしまう。
たとえば、まだ商品を出荷していないのに「売れた」として記録してしまう。
もちろん見かけ上は、売上が伸びてるように見えます。でも翌月にはその分が減るので、帳尻は合いません。
これを繰り返すと、いつか“粉飾決算”になります。
2:費用を資産にすり替える
たとえば、広告費や研究開発費といった「普通は費用になるお金」を、会社の“資産”として扱うとどうなるか。
費用にすれば利益は減りますが、資産にすれば減りません。つまり、「本当は利益が少ないのに、あるように見せかけられる」ってわけです。
見た目は良い。でも、実態はヤバい。
3:棚卸資産を操作する
在庫が大量にある会社でよく使われる手です。
「売れてない商品」を「まだ価値がある」と言い張って、損失を先延ばしにします。
でも現実にはその商品、売れずに廃棄されたり、値引きされる可能性が高い。
つまり「本当の資産価値」はないのに、あるように見せてるだけです。
数字の裏を見る「3つの目」を持とう
著者たちは「見かけにだまされず、財務諸表を正しく読み解くスキル」が必要だと言っています。
そこで紹介されていた、特に重要な3つのポイントを簡単にまとめます。
1:キャッシュフローを見る
企業がどれだけ現金を生み出してるかを見る「キャッシュフロー計算書」は、意外と正直です。
ごまかされた売上や利益があっても、キャッシュフローが悪ければ要注意。
特に「営業キャッシュフロー」がマイナスの企業は、要警戒です。
2:利益とキャッシュに差がないか確認
たとえば「純利益が増えてるのに、営業キャッシュフローが減っている」なら、それは“数字の操作”の可能性があります。
利益と現金の動きにズレがある場合、その理由をちゃんと調べるクセをつけましょう。
3:注記や脚注を読むクセをつける
財務諸表の下の方にある「注記」や「補足説明」、めんどくさくて飛ばしがちですが、実はここに“トリックの種明かし”が書かれていることも。
数字のごまかしは、完全にバレないようにするのではなく、「こっそり書いておくことで責任逃れする」ケースもあります。
高校生にもできる“ウソを見抜く習慣”
高校生の方だと、いきなり財務諸表なんてピンとこないかもしれません。でも、騙されない力は“習慣”で身につきます。
たとえば、
・何かの数字を見たときに「この数字って本当に信用できるのかな?」と疑ってみる
・メディアやSNSで流れてくる情報をすぐに鵜呑みにしない
・「本当にそうなの?」と1回ブレーキをかけるクセをつける
これだけでも、将来お金の世界で大きく失敗するリスクはかなり減ります。
投資の世界では「信じすぎる人」が負ける
この本の真のメッセージは、「数字は万能じゃない」ってことです。
むしろ、都合よく“作られてしまう”からこそ、僕たちは疑ってかかる必要がある。
そしてその“疑う力”こそが、投資家としての武器になります。
かのウォーレン・バフェットも、「数字は出発点に過ぎない」と言っていました。
財務諸表の奥にある“ストーリー”を読み取れるかどうか。そこに、あなたの未来がかかっているのです。
まとめ:数字は“読める”より“見抜ける”が大事
『会社の数字はウソをつく』は、決算書の読み方というより「騙されない思考法」の本です。
・数字は“正確”ではなく“演出”されていることがある
・キャッシュフローや利益のズレに注目しよう
・注記や小さな違和感に目を向けよう
この3つのポイントを知るだけでも、あなたの“金融リテラシー”は一歩上のレベルに達します。
今後、企業に就職するにしても、株式投資を始めるにしても、「数字を見る目」は必須スキル。
でも大丈夫。今から学べば、ぜんぜん間に合います。
数字は、騙す道具にも、守る武器にもなるんです。

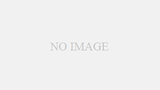
コメント